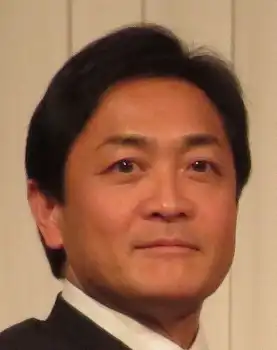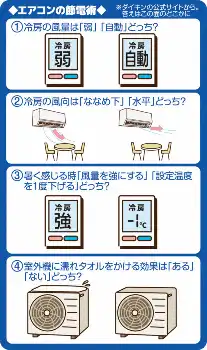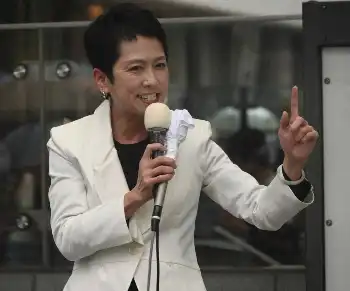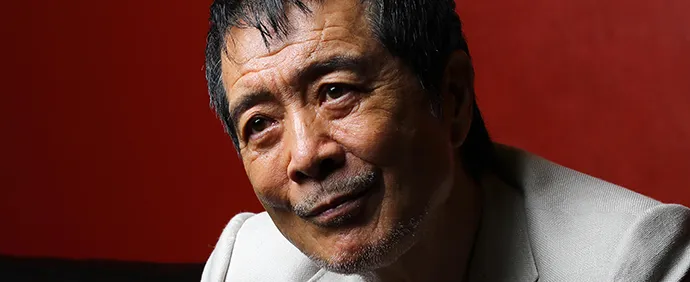競争激化!!手術支援ロボット開発 米Intuitive社「ダビンチ」独占も技術特許切れ
2024年06月03日 05:00
社会
がん治療の最前線、米国で働く日本人医師が現場から最新の情報を届ける「USA発 日本人スーパードクター これが最新がん治療」。テキサス州ヒューストンにある米がん研究最大の拠点「MDアンダーソンがんセンター」で治療に取り組む小西毅医師による第24回は、手術支援ロボットの開発競争の現状についてです。
≪最前線紹介≫
先日、米国の大手医療メーカーから、新しく開発した手術支援ロボットの試作品を評価してほしいと依頼を受けました。米国内の開発ラボに出向くと、ロボット手術で各国を代表する外科医たちが招へいされており、模型を使った模擬手術など、さまざまな角度から試作品を評価して改善点の討議を重ねました。試運転した印象ではかなり完成度が高く、今後市場に投入されればかなり競争が激化するだろうと感じました。
手術支援ロボットは長らく、米国のIntuitive(インテュイティブ)社の「ダビンチ」が独占状態で圧倒的な地位を占めていました。しかし、さまざまな技術の特許が切れたのに伴い、今や世界中で少なくとも40社以上が新しい手術支援ロボットを開発しています。これに対しIntuitive社も今年、ダビンチ5という最新機種を発売しました。MDアンダーソンもこの夏に複数台購入し、私も臨床使用を開始する予定です。本日は、このように競争が激化する手術支援ロボットの最前線をご紹介します。
≪視覚の進化≫
手術支援ロボットは解像度の高い3Dカメラが標準装備のため、従来の腹腔(ふくくう)鏡手術の2D画像に比べると立体感覚が失われません。このため、体の奥深い場所でも自由に縫合などの細かい操作が可能になります。これに加えて重要なのが、肉眼では見えないものを見ることができる蛍光カメラモードです。特殊な蛍光ライトを当てると発光するICGという薬を注射して、血流の良さを評価したり、ICGが排せつされる胆管の解剖をくっきりと認識するなど、さまざまな方法で手術に役立ちます。
最新のロボットではICGからさらに進化した薬剤を利用し、脂肪組織に埋もれたがん組織を光らせるなど、肉眼では見えないさまざまなものを光らせて手術で取るもの、残すものを、より鮮明に可視化する機能が開発されています。
もう一つ実現が近いのは、術前に撮影したCTやMRIなどの画像を手術中のカメラ画像に重ね合わせる技術です。手術で残すべき血管や神経、切除すべきがん組織などをリアルタイムで手術中の画面に映し出すことで、より安全に手術できるようになります。
しかし、人の組織は手術中の体位や操作などさまざまな条件で伸び縮みするため、手術前の画像を手術中の画面に単純に重ね合わせただけでは、ぴったりと合いません。最新の技術ではAIを用いたリアルタイム画像認識で大きさや位置を補正し、手術中の画面に正確に投影します。携帯電話の動画アプリで人の顔が簡単にネコやイヌにリアルタイムで変えられるように、AIの画像認識は凄い速度で進化しています。つい数年前まで、術前画像の投影は誤差が1センチ以上と実用に程遠かったですが、現在はかなり正確になっています。
≪触覚の進化≫
ロボット手術の最大の弱点は触覚がないことです。このため初心者のうちは、強い力を加えすぎて組織を傷めたり、出血させる危険があります。先日、東京医科歯科大学と東京工業大学が共同開発した、触覚を伝える手術支援ロボットが話題となりました。今年発売のIntuitive社のダビンチ5にも、触覚を伝える機能が搭載されます。
私たち外科医の手は、とても繊細にトレーニングされており、触覚を頼りに小さな腫瘍を見つけたり、弱い組織を微妙に感じ取って損傷しないよう優しく扱うことができます。これまで視覚に頼りっ放しだったロボット手術に触覚が加われば、余分な力を加えない安全な手術はもちろん、より繊細で正確な手術が可能になってきます。
≪多関節の進化≫
ロボット手術は自由に曲がる関節があり、人の手では不可能な角度の操作が行えます。特に骨盤深くなど、体の奥深く狭い場所で強みを発揮します。近年、自由に湾曲するフレキシブルな関節を持ち、体にたった1カ所の小さな穴を開けるだけで、そこから何本もの細い操作アームを体内へ入れて操作できるロボットが開発されました。単孔式といわれる手術方法で、ロボットで行わないとかなり難しい手技です。Intuitive社のダビンチSPが先駆ですが、他にもボディー全体がヘビのようにくねくね曲がって体に入っていくことができる軟性内視鏡型のロボットなど、新たな機種が開発されています。
≪日本のロボット≫
産業用ロボットの老舗である川崎重工と、医療分野に強いシスメックスが共同設立した会社メディカロイドから発売された「hinotori(ヒノトリ)」は、日本で薬事承認され臨床使用された最初の手術支援ロボットです。日本人の外科医、患者に合うよう小さくコンパクトに作られており、外科医の操作するコックピットも人間工学に基づき疲れにくいデザインとなっています。従来のダビンチに比べると値段が安価で、医療経済への負担が少ないのが特長です。
このほか、国立がん研究センター東病院外科部長の伊藤雅昭先生が率いるベンチャー部門が開発した手術支援ロボットは、助手の役割をロボットがこなし、術者1人で腹腔鏡手術ができるようデザイン、開発され、薬事承認されました。トヨタの車や川崎重工の産業用ロボットのように、日本の医療ロボットも世界を相手に戦える日が来るか、し烈な開発競争が続いています。
◇小西 毅(こにし・つよし)1997年(平9)、東大医学部卒。東大腫瘍外科、がん研有明病院大腸外科を経て、2020年から米ヒューストンのMDアンダーソンがんセンターに勤務し、大腸がん手術の世界的第一人者として活躍。大腸がんの腹腔鏡・ロボット手術が専門で、特に高難度な直腸がん手術、骨盤郭清手術で世界的評価が高い。19、22年に米国大腸外科学会Barton Hoexter MD Award受賞。ほか学会受賞歴多数。
先日、米国の大手医療メーカーから、新しく開発した手術支援ロボットの試作品を評価してほしいと依頼を受けました。米国内の開発ラボに出向くと、ロボット手術で各国を代表する外科医たちが招へいされており、模型を使った模擬手術など、さまざまな角度から試作品を評価して改善点の討議を重ねました。試運転した印象ではかなり完成度が高く、今後市場に投入されればかなり競争が激化するだろうと感じました。
手術支援ロボットは長らく、米国のIntuitive(インテュイティブ)社の「ダビンチ」が独占状態で圧倒的な地位を占めていました。しかし、さまざまな技術の特許が切れたのに伴い、今や世界中で少なくとも40社以上が新しい手術支援ロボットを開発しています。これに対しIntuitive社も今年、ダビンチ5という最新機種を発売しました。MDアンダーソンもこの夏に複数台購入し、私も臨床使用を開始する予定です。本日は、このように競争が激化する手術支援ロボットの最前線をご紹介します。
≪視覚の進化≫
手術支援ロボットは解像度の高い3Dカメラが標準装備のため、従来の腹腔(ふくくう)鏡手術の2D画像に比べると立体感覚が失われません。このため、体の奥深い場所でも自由に縫合などの細かい操作が可能になります。これに加えて重要なのが、肉眼では見えないものを見ることができる蛍光カメラモードです。特殊な蛍光ライトを当てると発光するICGという薬を注射して、血流の良さを評価したり、ICGが排せつされる胆管の解剖をくっきりと認識するなど、さまざまな方法で手術に役立ちます。
最新のロボットではICGからさらに進化した薬剤を利用し、脂肪組織に埋もれたがん組織を光らせるなど、肉眼では見えないさまざまなものを光らせて手術で取るもの、残すものを、より鮮明に可視化する機能が開発されています。
もう一つ実現が近いのは、術前に撮影したCTやMRIなどの画像を手術中のカメラ画像に重ね合わせる技術です。手術で残すべき血管や神経、切除すべきがん組織などをリアルタイムで手術中の画面に映し出すことで、より安全に手術できるようになります。
しかし、人の組織は手術中の体位や操作などさまざまな条件で伸び縮みするため、手術前の画像を手術中の画面に単純に重ね合わせただけでは、ぴったりと合いません。最新の技術ではAIを用いたリアルタイム画像認識で大きさや位置を補正し、手術中の画面に正確に投影します。携帯電話の動画アプリで人の顔が簡単にネコやイヌにリアルタイムで変えられるように、AIの画像認識は凄い速度で進化しています。つい数年前まで、術前画像の投影は誤差が1センチ以上と実用に程遠かったですが、現在はかなり正確になっています。
≪触覚の進化≫
ロボット手術の最大の弱点は触覚がないことです。このため初心者のうちは、強い力を加えすぎて組織を傷めたり、出血させる危険があります。先日、東京医科歯科大学と東京工業大学が共同開発した、触覚を伝える手術支援ロボットが話題となりました。今年発売のIntuitive社のダビンチ5にも、触覚を伝える機能が搭載されます。
私たち外科医の手は、とても繊細にトレーニングされており、触覚を頼りに小さな腫瘍を見つけたり、弱い組織を微妙に感じ取って損傷しないよう優しく扱うことができます。これまで視覚に頼りっ放しだったロボット手術に触覚が加われば、余分な力を加えない安全な手術はもちろん、より繊細で正確な手術が可能になってきます。
≪多関節の進化≫
ロボット手術は自由に曲がる関節があり、人の手では不可能な角度の操作が行えます。特に骨盤深くなど、体の奥深く狭い場所で強みを発揮します。近年、自由に湾曲するフレキシブルな関節を持ち、体にたった1カ所の小さな穴を開けるだけで、そこから何本もの細い操作アームを体内へ入れて操作できるロボットが開発されました。単孔式といわれる手術方法で、ロボットで行わないとかなり難しい手技です。Intuitive社のダビンチSPが先駆ですが、他にもボディー全体がヘビのようにくねくね曲がって体に入っていくことができる軟性内視鏡型のロボットなど、新たな機種が開発されています。
≪日本のロボット≫
産業用ロボットの老舗である川崎重工と、医療分野に強いシスメックスが共同設立した会社メディカロイドから発売された「hinotori(ヒノトリ)」は、日本で薬事承認され臨床使用された最初の手術支援ロボットです。日本人の外科医、患者に合うよう小さくコンパクトに作られており、外科医の操作するコックピットも人間工学に基づき疲れにくいデザインとなっています。従来のダビンチに比べると値段が安価で、医療経済への負担が少ないのが特長です。
このほか、国立がん研究センター東病院外科部長の伊藤雅昭先生が率いるベンチャー部門が開発した手術支援ロボットは、助手の役割をロボットがこなし、術者1人で腹腔鏡手術ができるようデザイン、開発され、薬事承認されました。トヨタの車や川崎重工の産業用ロボットのように、日本の医療ロボットも世界を相手に戦える日が来るか、し烈な開発競争が続いています。
◇小西 毅(こにし・つよし)1997年(平9)、東大医学部卒。東大腫瘍外科、がん研有明病院大腸外科を経て、2020年から米ヒューストンのMDアンダーソンがんセンターに勤務し、大腸がん手術の世界的第一人者として活躍。大腸がんの腹腔鏡・ロボット手術が専門で、特に高難度な直腸がん手術、骨盤郭清手術で世界的評価が高い。19、22年に米国大腸外科学会Barton Hoexter MD Award受賞。ほか学会受賞歴多数。